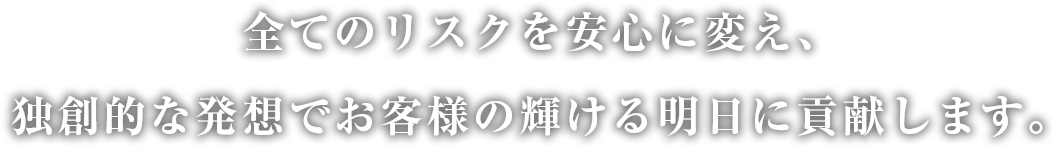
リスクコンサルティングで
お客様が輝く明日を共に目指す
インターネット・SNSの普及で、情報過多となった今、
お客様にとって何が正しい情報であるのか、見極めることが難しい時代となりました。
この大きな変化の中で、企業も変化し続けなければ、いつか淘汰されてしまいます。
そのような数年先を予測することも困難な今こそ、
お客様の立場に寄り添い、独創的な発想と最適なソリューションを提供することで、
お客様の繁栄に刺激を与えることが重要であると私たちは考えます。
JCMは、中小企業・個人事業主の皆様へのリスクコンサルティングに特化することで
これまで培った様々な業種へのご提案の経験と実績を最大限に生かし、
「三意(熱意・誠意・創意)」と「素直な心」で、経営者の皆様を支えていきます。


(JAPAN CRISIS MANAGEMENT Co.,ltd)
〒351-0025 朝霞市三原 1-4-3 KRコンフォートビル 202
フリーダイヤル : 0120-768349 (ナローヤサシク)
Tel : 048-423-9944(代表)
Fax : 048-423-9941